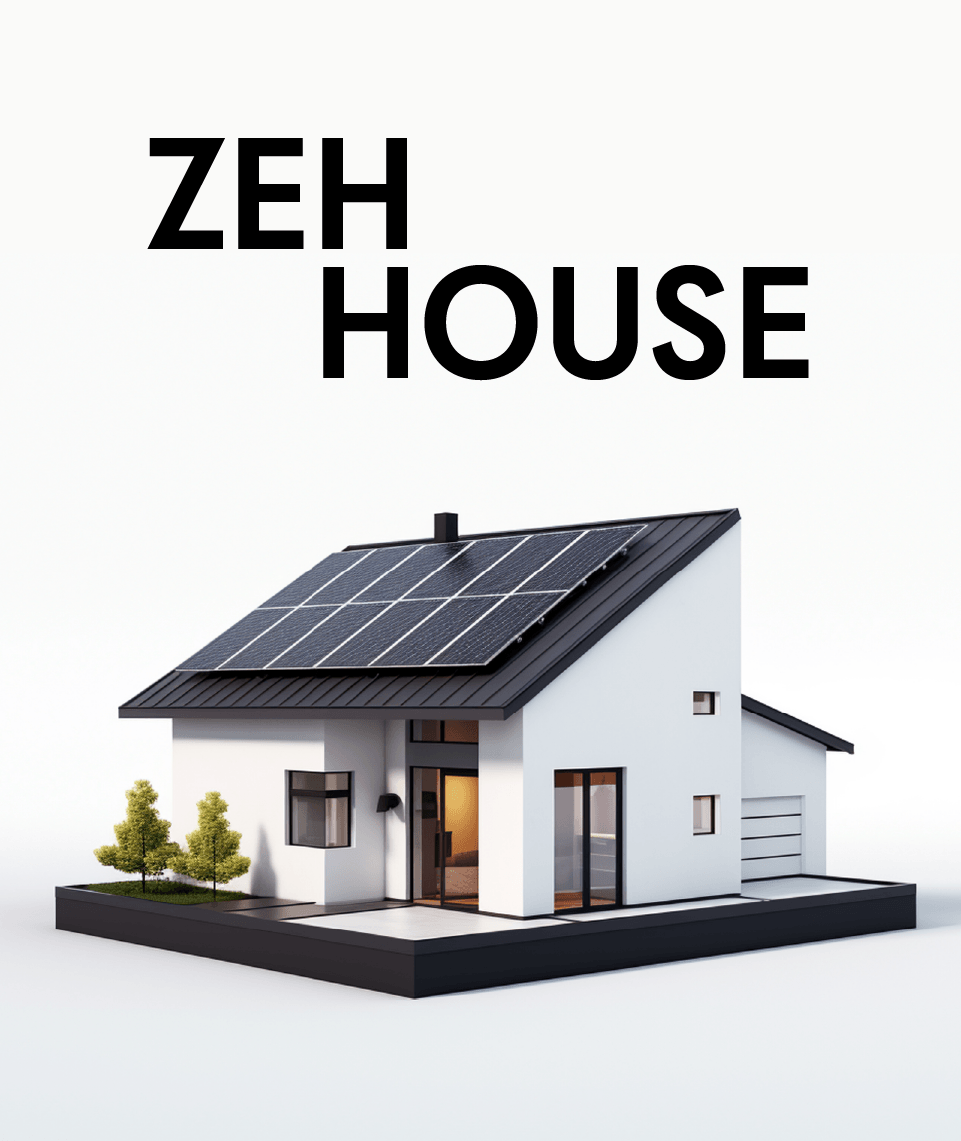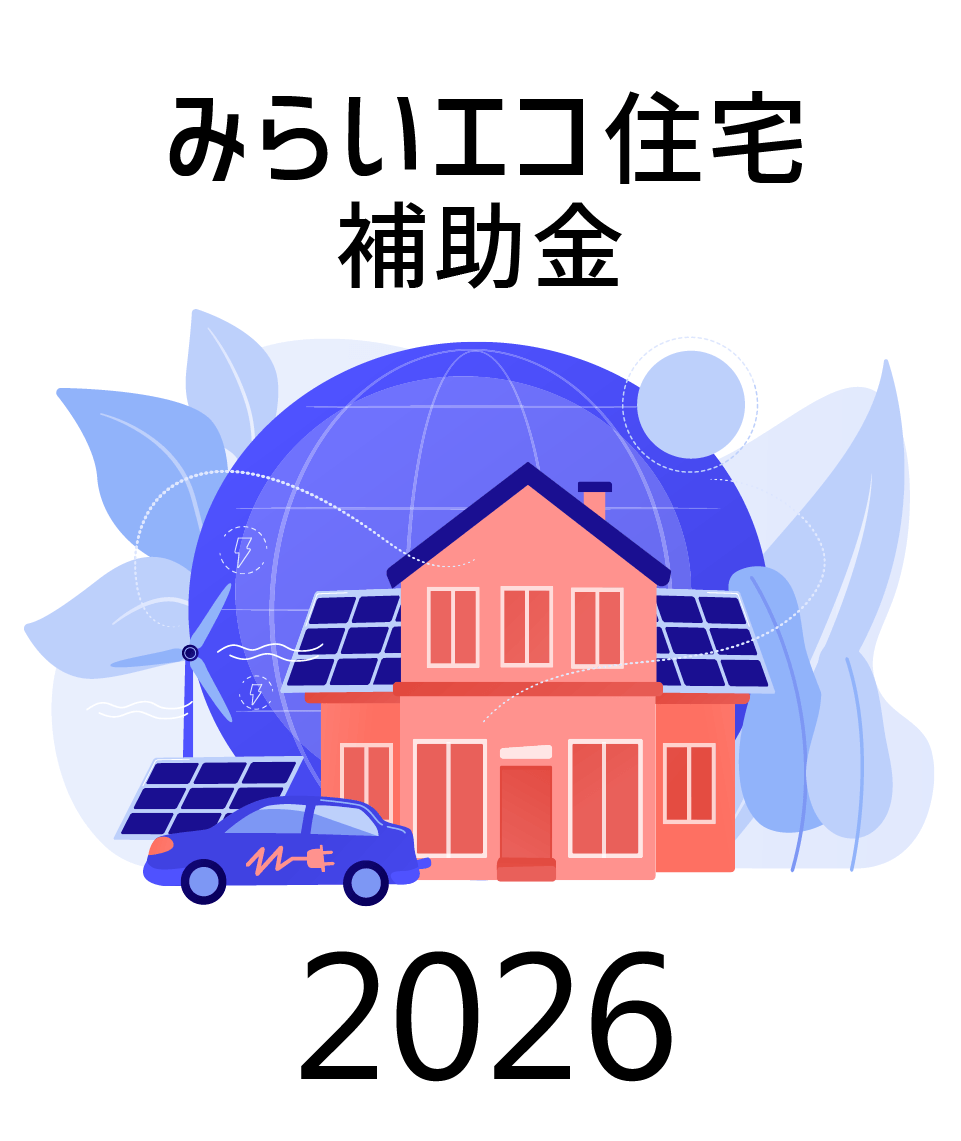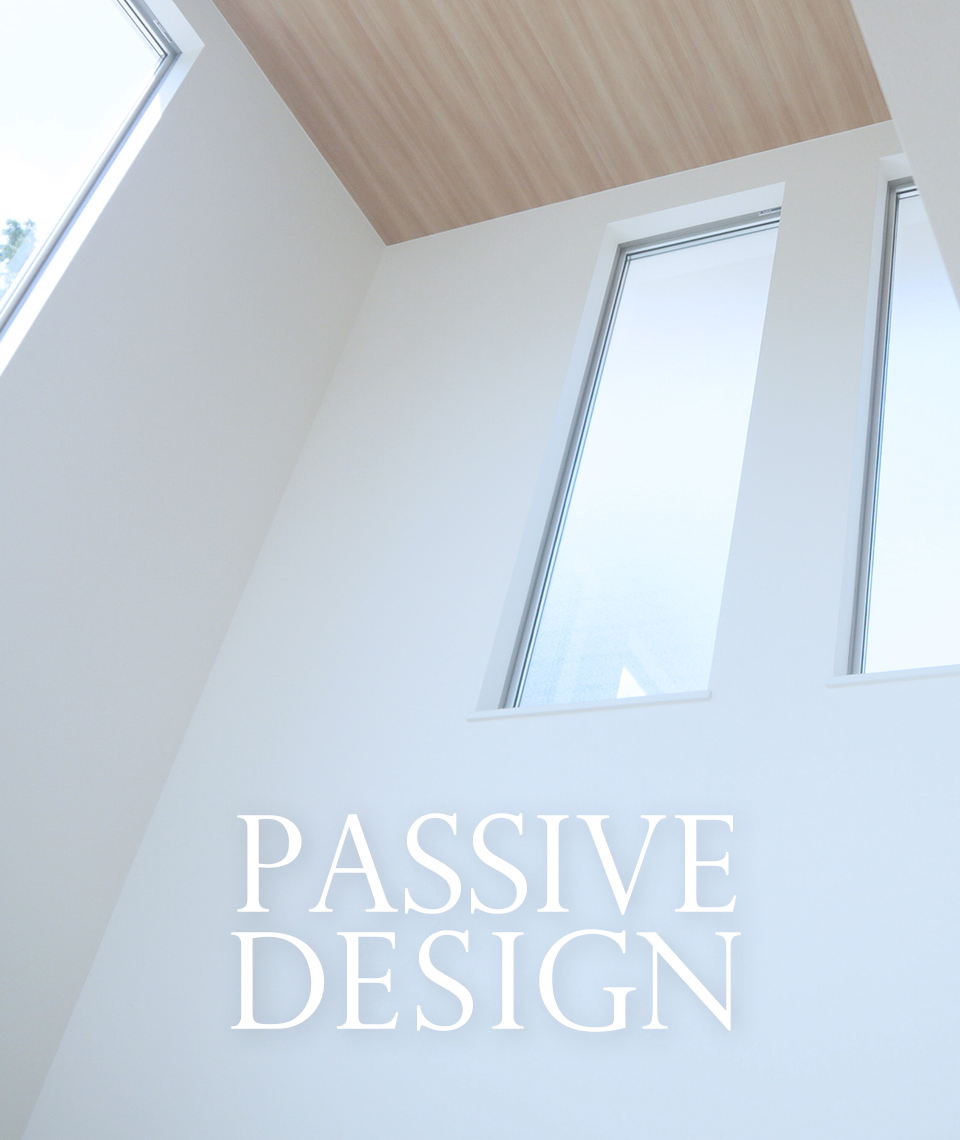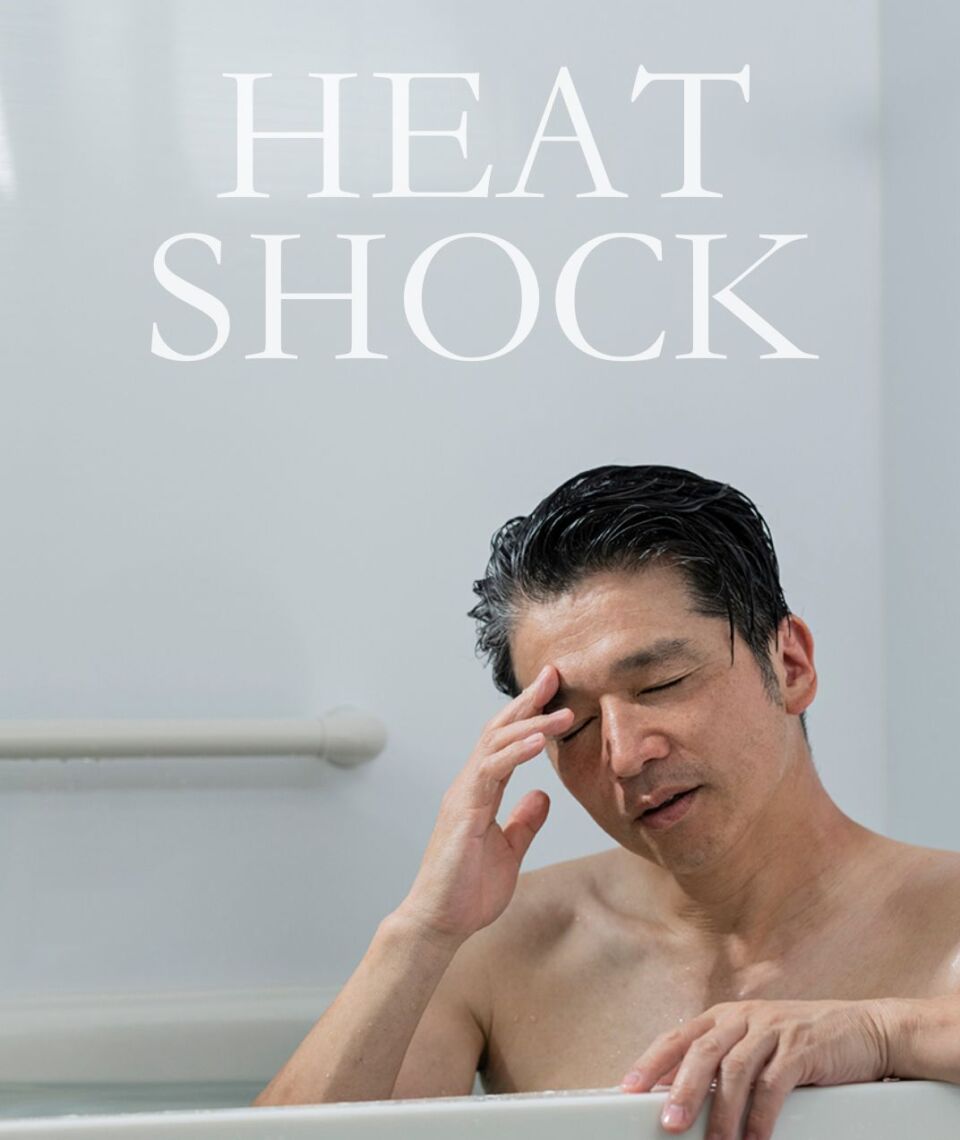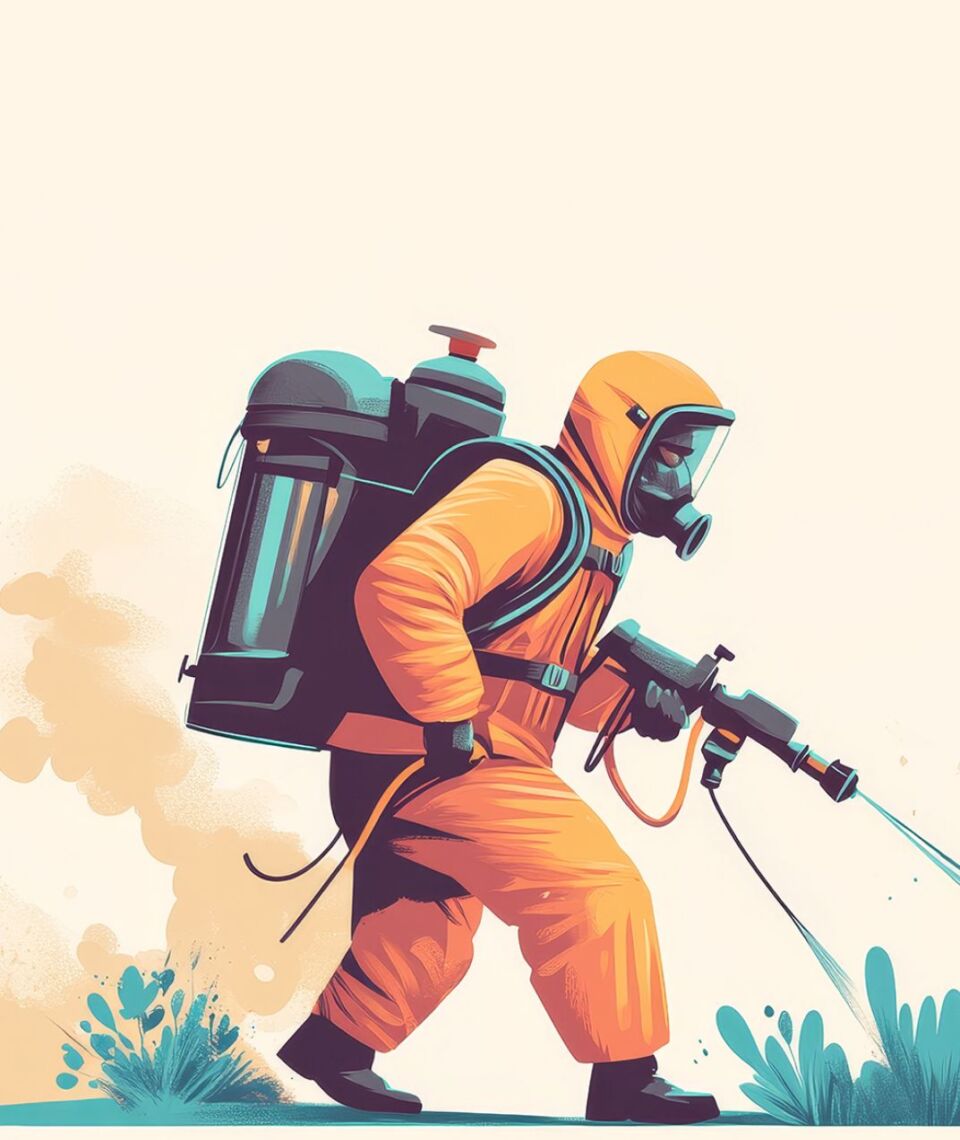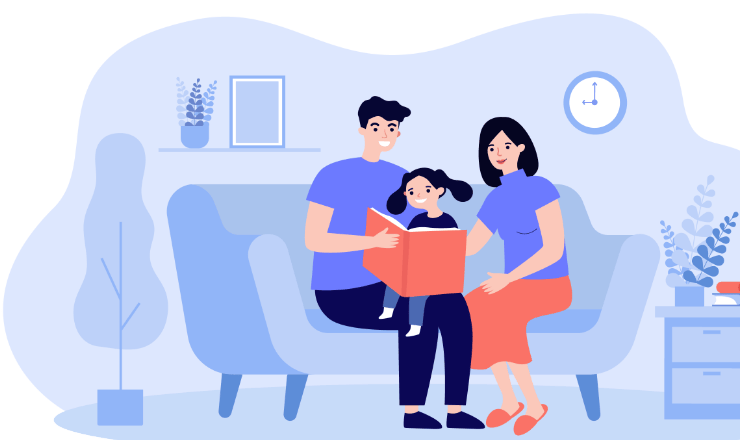HIGH PERFORMANCE
HOUSE
高性能住宅
結露の原因と防止策をチェック!
家を守るためにできること
寒い季節に多く見られる「結露」の原因や対策を解説。
放置するとカビや家の劣化、シロアリ被害につながることもあります。
快適な住環境を守るための防止策を紹介します。
寒い季節になると、窓ガラスに水滴がびっしりとつく「結露」に悩まされる方も多いのではないでしょうか?結露は見た目が気になるだけでなく、放置するとカビの発生や家の劣化につながることもあります。さらに、ひどい場合にはシロアリ被害の原因になることも。
では、なぜ結露は発生するのでしょうか?
また、結露を防ぐためにはどんな対策が効果的なのでしょうか?
この記事では、結露の仕組みや二次被害、そして家を守るための具体的な防止策について詳しく解説します。家の寿命を延ばし、快適な住環境を維持するために、ぜひチェックしてみてください!
結露とは?なぜ発生するのか

結露とは、空気中の水蒸気が冷やされて水滴となる現象のことです。
冬の朝、窓ガラスに水滴がついているのを見たことがある方も多いでしょう。これは、室内の暖かく湿った空気が、外気で冷えた窓に触れることで冷やされ、空気中に含みきれなくなった水蒸気が水滴となって現れるためです。
結露が発生する主な原因は、「温度差」と「湿度」の2つです。室内と屋外の温度差が大きく、なおかつ室内の湿度が高いと、結露が発生しやすくなります。特に冬場は、暖房で室内が暖められる一方で、窓や壁の表面は外気の影響を受けて冷えやすくなるため、室内の水蒸気が冷やされて結露が起こる状況が整ってしまうのです。
また、結露は窓ガラスだけでなく、壁の内部や床下など見えない場所でも発生することがあります。断熱が不十分な住宅では、壁の内側に結露ができ、それが原因でカビや木材の腐朽を引き起こすことも。気づかないうちに家の寿命を縮める原因となるため、室内で発生した水蒸気が建物の内部に浸透しないよう事前に予防策を取り、適切な対策を講じることが重要です。
結露による二次被害とは?

結露は単に窓が濡れるだけの現象ではなく、放置するとさまざまな二次被害を引き起こします。特に、カビの発生、木材の腐朽、そしてシロアリ被害には注意が必要です。
カビ・ダニの発生と健康への影響
結露によって常に湿った環境ができると、カビやダニが発生しやすくなります。窓のサッシやカーテン、壁紙の裏などに黒カビやダニが繁殖すると、見た目が悪くなるだけでなく、アレルギーや喘息、シックハウス症候群などの健康被害を引き起こすことも。特に、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、室内のカビ対策が重要です。
木材の腐朽(腐れ)
壁の内部や床下で発生した結露は、建材に影響を与えます。特に、木材が長期間湿った状態になると、木が腐朽(腐れ)し、家の耐久性が低下します。木材が劣化すると、床がきしんだり、壁に歪みが出たりと、建物全体の構造にも悪影響を及ぼします。
シロアリ被害
木材の腐朽が進むと、それをエサとするシロアリが発生するリスクも高まります。シロアリは木材の内部を食い荒らし、家の強度を著しく低下させます。最悪の場合、大規模な修繕が必要になることも。結露が原因でシロアリ被害に発展するケースも少なくないため、早めの対策が重要です。
結露は見た目には小さな問題に思えますが、放っておくと住宅の寿命を縮め、修繕費用がかさむ原因になります。特に、壁の内部や床下の結露は気づきにくいため、日頃から対策を意識することが大切です。
結露を防ぐための対策
結露を防ぐには、「室内の湿度を下げる」「温度差を小さくする」という2つのポイントを意識することが重要です。以下の具体的な対策を実践することで、結露の発生を予防し、発生を抑えることができます。
室内の換気を意識する
室内に湿気がこもると結露が発生しやすくなるため、こまめに換気を行うことが大切です。1日2〜3回、窓を開けて空気を入れ替えることで、湿気を外に逃がしやすくなります。特に冬場は寒さを理由に換気を怠りがちですが、短時間窓を開けるだけで効果があります。
また、キッチンや浴室、トイレなど湿気がこもりやすい場所では換気扇を積極的に活用しましょう。さらに、寝室では人の呼吸によって湿度が上がるため、朝起きたら必ず窓を開けて換気を行うと、結露の発生を抑えられます。
加湿を控え、湿度を適正に保つ
結露の発生を防ぐには、室内の湿度を適正な範囲(40〜60%)に保つことが重要です。湿度計を活用してこまめに湿度を確認し、必要以上の加湿を控えるようにしましょう。
加湿器を使用する際は、窓や壁に水滴がついていないかチェックしながら調整することが大切です。また、洗濯物を室内に干すと湿度が急激に上がるため、可能であれば外干しにするか、除湿機や換気扇を併用して湿気を抑える工夫をしましょう。
窓や壁の断熱性を高める
室内外の温度差が大きいと結露が発生しやすくなるため、窓や壁の断熱性を高めることはとても有効です。手軽な方法としては、窓に結露防止シートを貼ることで断熱効果を高めることができます。
また、厚手のカーテンや断熱カーテンを使用すると、窓からの冷気を遮断し、室内の温度を安定させるのに役立ちます。さらに、リフォームを検討する際には、壁や床に断熱材を入れることでより効果的に結露を防ぐことができます。
除湿アイテムを活用する
除湿アイテムを活用するのも効果的です。冬場は特に湿度が高くなりやすいため、除湿機を使用すると結露の発生を抑えやすくなります。
また、シリカゲルや炭、珪藻土などの自然素材を利用した除湿アイテムをクローゼットや窓際に置くと、手軽に湿気対策ができます。さらに、市販の結露防止シートやスプレー、吸水テープを活用することで、サッシの結露対策を強化できます。
家具の配置を工夫する
家具の配置を工夫することで、結露の発生を抑えることができます。
特に、壁に密着した家具の裏側は空気が滞留しやすく、湿気がこもることでカビの発生リスクが高まります。そのため、家具は壁から5cm以上離して設置し、空気の流れを確保することが重要です。また、押し入れやクローゼット内も湿気がこもりやすいため、定期的に扉を開けて換気を行うと良いでしょう。さらに、除湿剤を活用することで、湿気の吸収を助け、カビの発生を防ぐことができます。
結露は、ちょっとした工夫を積み重ねることで防ぐことができます。「湿気をこもらせない」「温度差を小さくする」という基本を意識しながら、日々の生活の中でできる対策を取り入れてみましょう。
家を建てる際に考えたい結露対策

家を建てる際には、結露が発生しにくい構造や設備を取り入れることが大切です。
結露は、単なる窓ガラスの水滴にとどまらず、壁の内部や床下で発生すると建材の腐食やカビの発生を引き起こし、家の寿命を縮める原因となります。
そのため、長く快適に住める家を作るためには、「断熱性の向上」「気密性と換気のバランス」「調湿機能の活用」という3つのポイントを意識することが重要です。
二重・三重窓を採用し、断熱性を高める
窓は外気の影響を受けやすく、結露が発生しやすい場所のひとつです。
そのため、新築時には「二重窓」や「三重窓」を採用することで、窓の断熱性を高めると効果的です。二重窓とは、室内側にもう一枚窓を設けることで空気の層を作り、室外と室内の温度差を緩和する構造のことです。特に、樹脂製の窓枠やLow-E複層ガラスを採用すると、より断熱性能が向上し、ガラスやサッシの温度を下げにくくなり、結露の発生を抑えることができます。
気密性を高めつつ、適切な換気システムを導入する
家の気密性が高いと、室内の暖かい空気が外に逃げにくくなり、省エネ効果が高まります。しかし、換気が不十分だと湿気がこもり、結露が発生しやすくなるため、「気密性」と「換気」のバランスを取ることが重要です。
現在のほとんどの住宅では、24時間換気システムが導入されているので、常に室内の空気を入れ替え、湿気をコントロールすることができます。特に、熱交換型の換気システムを採用すれば、室温を極端に下げることなく換気ができるため、冬場の結露対策としても有効です。
断熱材や調湿建材を活用する
壁や床の内部で発生する「内部結露」を防ぐためには、適切な断熱材を使用することが重要です。
断熱、調湿、防音に非常に優れたセルロースファイバーと、天然岩石を主原料とし保温だけではなく防火・耐火に非常に優れているロックウールを使用すると、壁内に湿気が溜まることはなく、日本の高温多湿な気候でも快適に過ごすことができます。
高性能な断熱材を採用すると、外気温の影響を受けにくくなり、壁の中での結露を防ぐことができるでしょう。このように壁、窓、床、屋根等に工夫を施すことで、室内の湿度を一定に保つことができ、結露の発生を抑える効果が期待できます。
床下や屋根裏の湿気対策を行う
結露は窓や壁だけでなく、床下や屋根裏でも発生することがあります。特に、床下の湿気がこもると、カビやシロアリの発生原因となるため、基礎部分の湿気対策をしっかり行うことが大切です。
効果的な方法としては、床下換気口の設置や、防湿シートを敷くことで湿気を抑えることができます。また、屋根裏の断熱材を強化し、外気の温度変化が直接影響しにくい構造にすることで、屋根裏の結露を防ぐことができます。
家を建てる際には、「断熱・気密・換気」のバランスを考え、適切な設備や素材を選ぶことで、結露を防ぐことができます。結露対策をしっかり行うことで、カビや木材の腐食、シロアリ被害を防ぎ、家の寿命を延ばすことにつながります。
結露を放置すると家の価値が下がる?

結露を「窓が濡れるだけの現象」と軽く考えていませんでしたか?
結露による湿気が住宅の構造や内装にダメージを与え、長期間放置すると壁の腐食やカビの発生、シロアリ被害に繋がることがわかりましたね。
結露を放置すると家の資産価値が下がる原因になりかねません。最悪の場合、家の耐久性が著しく低下し、修繕やリフォームに多額の費用がかかることもあります。ここでは、結露が家の価値に与える影響について詳しく解説します。
内装の劣化で住宅の印象が悪くなる
結露による水分が長期間窓枠や壁紙に染み込むと、黒ずみやカビが発生し、内装が汚れてしまいます。特に、壁紙が剥がれたり、木製の窓枠や床が変色・変形したりすると、室内の見た目が悪くなり、住宅の印象が大きく損なわれます。
また、中古住宅として売却を考えたとき、内装の劣化が目立つと買い手の印象が悪くなり、査定額が下がる原因になります。
建材の腐食が進み、家の耐久性が低下する
結露は目に見える部分だけでなく、壁の内部や床下にも発生することがあります。湿気がこもると、木材や断熱材が腐食し、家の強度が低下してしまいます。
特に、柱や梁などの構造部分が湿気によって劣化すると、住宅全体の耐久性が落ち、大規模な補修工事が必要になることもあります。
こうした建物の劣化は、住宅の資産価値を大きく下げる要因となります。
シロアリの被害で家の修繕費がかさむ
湿気が多い環境は、シロアリの大好物です。結露による湿気で床下や柱の木材が湿ると、シロアリが発生しやすくなり、建材を食い荒らしてしまいます。シロアリの被害が広がると、家の土台や柱が脆くなり、修繕のために高額な費用がかかることになります。
シロアリ被害がある家は売却時に査定額が大きく下がるため、結露による湿気対策を怠ることは、資産価値の低下にも直結する問題です。
売却時の査定額が下がる可能性がある
住宅を売却する際、買い手は家の状態やメンテナンス状況を細かくチェックします。結露が原因でカビや腐食が見られると、修繕が必要な物件と判断され、査定額が下がる要因になりかねません。特に、見た目だけでなく、壁の内部や床下の腐食が進んでいる場合、買い手は大きなリスクを感じ、価格交渉で大幅な値引きを求められる可能性もあります。
結露を放置し適切な予防を怠ると、家の見た目の劣化だけでなく、建物の耐久性や資産価値にも大きな影響を及ぼします。大切な家を長持ちさせるためにも、日々の換気や断熱対策をしっかり行い、結露の発生を防ぐことが重要です。
結露を防いで家を長持ちさせよう

結露をそのままにしておくと、カビの発生や木材の腐食を引き起こし、最悪の場合はシロアリ被害につながることもあります。こうした二次被害が進むと、住宅の耐久性が低下し、修繕費がかかるだけでなく、家の資産価値にも影響を及ぼします。そのため、結露の発生を確認したら、できる範囲で防止策を講じることが大切です。
結露対策としては、こまめな換気や湿度管理、断熱対策を意識することが重要です。特に、窓や壁の断熱性を高めることで、室内外の温度差を抑え、結露の発生を大幅に減らすことができます。また、加湿器の使い方を調整したり、除湿機や結露防止グッズを活用したりすることで、手軽に対策を強化することも可能です。
さらに、家を建てる際には、二重・三重窓を採用し、気密性と換気のバランスが取れた設計にすることで、結露のリスクを大幅に軽減できます。適切な断熱材や調湿機能のある建材を活用することも、長期的に快適な住環境を維持するためのポイントです。
結露は、小さな工夫で防ぐことができる身近な問題です。発生した際には放置せず、できる範囲で対策を行い、家を守る習慣をつけましょう。